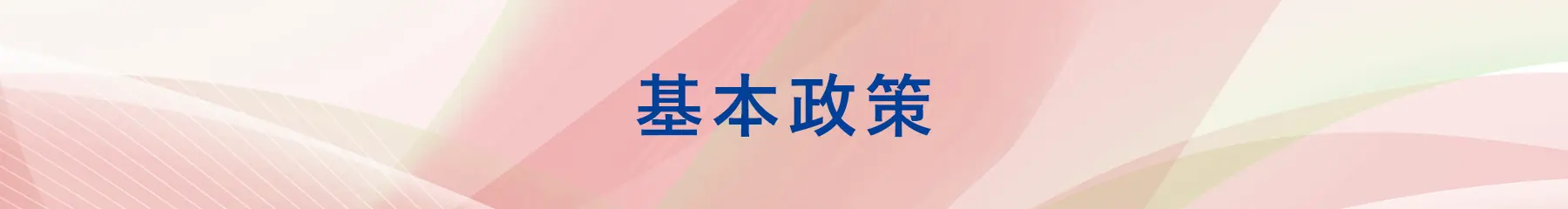

2011年3月11日を境に日本は大きく変わらなくてはならなかったはずです。2009年9月の政権交代後、当時の民主党は国民のみなさんの期待に十分に応えられませんでした。私が政治の世界に入って30年以上が経過しました。やっと実現した政権交代にもかかわらず、その後の状況は残念であり、申し訳ない気持ちで一杯です。今こそ、2017年秋、小池百合子東京都知事が求めたような「保守二大政党」体制ではなく、きちんとした対抗軸をもったもうひとつの政党を育てていかなければならないと思います。
東日本大震災で多くの方が命を失い、また、今なお厳しい避難生活を強いられている方がどれほど大勢いらっしゃることでしょうか。さらには、今後の復興再生という点でも容易ではない。解決しなくてはならない課題はあまりにも多いのです。
今こそ、私たちは、この未曾有の巨大災害と新型コロナウイルス感染症のような未知の敵に対して全英知を総動員しなくてはならないはずです。
東京電力福島第一原子力発電所事故について、今、必要なのは評論ではなく行動と実践であり、事故終息に向けた真の分析・対応ではないでしょうか。確かに時の政権の課題は少なくはない。しかし、例えば「原子力問題」について、このシステムをつくり維持してきたのは、間違いなくこれまでの自民党政権であるはずです。もちろん、政権交代後、まっさきに解決しなかった民主党にも大きな責任があります。だからこそ、与野党を超えた議論と行動を起こさなければならないのです。
私たちは「福島原発事故で日本国の威信が世界の中で地に堕ちた」という事実をはっきりと認識しなくてはいけません。政争を続けている暇はないのです。

「津波の被害」は天災ではなく、これは、明らかに人災ではないでしょうか。独立行政法人産業技術総合研究所の岡村行信活断層・地震研究センター長や経産省所管の原子力安全基盤機構の警告を無視したのは東京電力でした。また、私も、現地に行って驚きましたが、気仙沼から三陸海岸の要所要所に掲げられた道路標識「ここより津波警戒地域」「ここまで津波警戒地域」は何を物語っているのでしょうか?行政府の責任は極めて重い。一方で危険性の指摘もされていた地域の開発を進めた民間の会社は何を考えていたのでしょうか。
1945年8月15日を境に、「戦前は云々」とか「戦後は云々」などと語られてきたように、これからは徐々に「震災前は」「震災後は」と語られるようになるのではないでしょうか。そして、そのようにしなくてはならないと思います。
戦前の日本は一時、戦争の勝利に酔い痴れ、戦後の日本は高度成長という経済戦争の勝利に酔い痴れ、大切なものを見失ったように思います。
物心付いてこの時代を生きてきた全ての日本人はそれぞれの立場で考えなくてはならないでしょう。即ち、「過去」への反省なき「現在」は、「未来」につながっていかない。
日本は、この先どうなるのか?今日一日が不透明、何が起きるか分からない。しかし、それは「震災事故」以前からの自然界の普遍の真理でした。ならば、質実に一生懸命、今日を生きるしかないと痛切に感じます。
そして、この国が生き抜けるとしたら、「資本主義vs共産主義」などという二元論を一日も早く卒業して、「競争のしたい者は自由に競争し、競争を拒否してマイペースで生きたい者も自由に生きられる国」をめざすべきです。
私のめざす新しい国づくりの政府は、少なくとも「減税の政府」ではない。「減税」は弱肉強食の競争を国是とし「自己責任のみが先行する国家」を究極にはめざすことになるからです。「大きな政府」の全てが問題ありとは思いませんが、バラまき型に陥りやすい。今、求めるべきは、競争はするが、普通にやっていけばなんとかやっていける社会システムを備えた「中くらいの政府」です。そして、その国に敢えて命名するとしたら「平和的福祉国家」だと思います。
そうした「全ての人が供に生きる国づくり」を、この格差が広がり、多くの人が不安の中で暮らしている日本で、私は求めていく。
(2023年7月記)