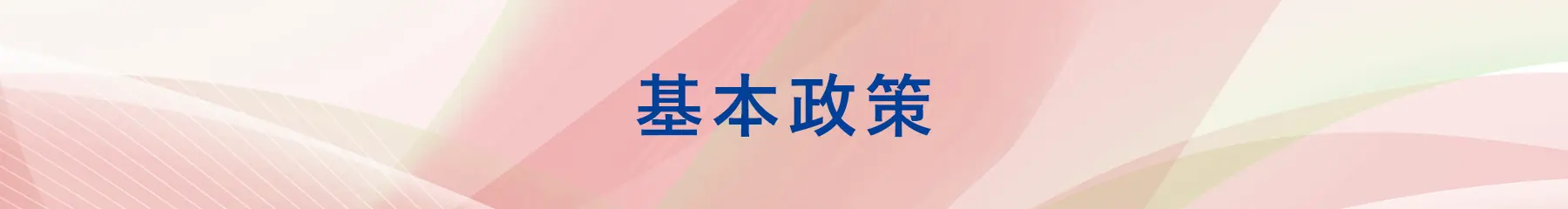

私が政治の世界に入るために中日新聞社を退社したのは、1993年1月31日のことでした。
名古屋市議であった近藤昭夫を父親にもった私は、政治に対する大きな関心がありました。しかしながら日頃の政治活動や政策の中身ではなく、地盤・看板・カバン(知名度・組織力・資金力の大小)で得票の多くが決まってしまう選挙に疑問を持っていました。そこで、私自身は、父親から学んだ「社会の公正のために」ということを、新聞というものを通じて実現したいと考えていたのです。
それが、細川護熙さんの日本新党が出現し新党運動が起きた時に、変わりました。「やはり政治を変えなくてはならない。そのためには傍観者ではなく、その渦の中でがんばりたい」と決心したのです。それは、日本だけではなく、世界中が大きな曲がり角に来ていると思ったからでもありました。
戦後の高度経済成長の中で日本は、世界一豊かな国、世界中が羨む「経済一流の国」になったと言われました。そして、「失われた10年」と言われ、「改革なくして成長なし」と小泉純一郎首相(当時)が規制改革と郵政民営化をうたった2000年代初頭でも、GDP(国内総生産)は4兆ドルを超え、アメリカ(10兆197億ドル)に次いで世界第2位でした。ところが、日本を熱狂の渦に巻き込んだ小泉改革を経ても経済成長は十分に回復することなく、リーマンショックと東日本大震災を経てさらに厳しい情勢が続いています。2010年にはGDPで中国が上回り、その差は今や3倍に開いています。国民一人当たりのGDPでは2000年に世界第2位だったものが、2022年は30位にまで下がっています。

国民生活を見た場合、金融行動世論調査によれば、2人以上の世帯で「金融資産ゼロ」の割合は2001年の16.7%から2021年には22%に増えています。そのうち、20代の世帯に限った場合、2021年は37%に達しており、若年層の貧困が深刻になっていることが分かります。全雇用者における非正規雇用者の割合は、2000年の26%が、2022年には36.9%に達しています。年収200万円未満のいわゆる「ワーキングプア」の割合も、2021年で21.4%(1,126万人)と深刻な数字を示しており、年収分布割合の最大部分は300~399万円の17.4%で、収入の二極分化も深刻です。生活保護受給者も1995年の88万人から増加し、2015年のピーク時には216万人に達し、2022年は約204万人となっています。
貧富の格差は拡大する一方にあり、日本の高度成長・発展とは一体何だったのかと考えざるを得ない状況になっています。
誰にでも、自分の力だけではどうにもならないことが必ずあります。今は勝ち組で、自分の力だけで生きていると思っている人でも、いつ不慮の病気や事故に見舞われるかわかりません。政治は、そのときのためにあります。自己責任を過度に強調してあおるとしたら、それは政治の責任放棄です。
2009年夏の総選挙で、「政権交代」が実現し、民主党政権が誕生しました。
政権交代後、「子どもは社会で育てる」をモットーとした「子ども手当」や「高校実質無償化」、「地方と国は平等」という観点による、基本的に地方が自由に使える「一括交付金」など、自民党政治とは違う、一人一人を大切にする政策を実現しました。しかし、その後の政権運営のつたなさや党内ガバナンスの未熟さから党が分裂し、再び自民党政権に戻らせてしまいました。そして安倍政権が8年近くも続き、自民党一強体制を許してしまっています。
しかし、このままでよいはずはありません。私の夢は、私のシンボルカラーであるオレンジ色のように「あたたかい国・元気な国」をつくっていくことです。アベノミクスはお金を増刷し、予算をバラ巻くことによって株価を操作しましたが、一人当たりの平均給与は低迷し、新型コロナウイルス感染症の爆発とウクライナ侵攻以降は厳しい物価高が進行し、2023年春闘では多くの企業で賃上げが実現しましたが、物価高には追いつかず、社会全体では格差が広がるばかりです。また、岸田政権は、閣議決定のみで戦後の防衛政策の根幹である専守防衛を転換し、軍拡増税を行おうとし、東京電力福島第一原発事故の教訓から原発の運転期間を定めた60年規制を超えても稼働を可能とする法改正を強行しました。さらに、憲法によってしばられている国会議員が自らをしばる憲法を変えようとしていますが、立憲主義は私たち政治家が守るべき基本です。憲法を守り、法に則り、国民の皆さんの声に耳を傾け、まっとうな政治を貫きます。
政治の役割は皆さんの声を受け止めて反映させることです。何としても、真の政治改革を実現して、以下に掲げる各論の目標を実現したいと思います。
(2023年7月記)